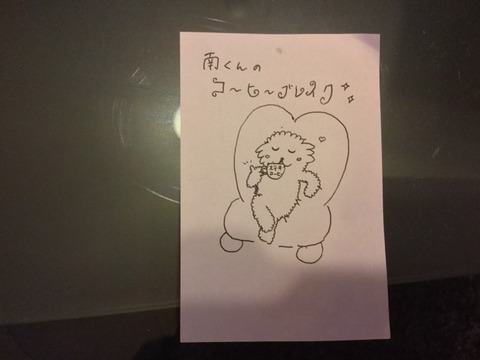僕はやはり過去からしか学べないんだなぁとつくづく思うのです。
あれはまだ僕が20代後半の頃の出来事です。
彼女と2人で当時流行っていた地下にあるお店で食事をしていました。
薄暗い店内はそこそこ賑わっており、ぼくたちは奥のテーブルに通されました。
他愛の無い話しをしながら食事を楽しんでいるとそこに
3人組の女性たちが、店内に入ってきたのです。
むむっ、どこかで会った女性!
そうです。異彩を放っていたその中の1人が、前カノだったのです。
それからというもの、彼女の話しは全く耳に入ってきませんでした。
彼女も僕の異変に気付いたらしく…。
語気を強めて
「ねぇ、チョット聞いてるの人の話。」
「どう思うの?」
どう思うのと聞かれても、話の内容を理解してない僕は困り果ててしまい
悪気は無かったのですがとっさに
「それはやっぱりパローレじゃない。」と言ってしまったのです。
どういう訳かBGMは、ハッキリと覚えておりました。
あの、パローレパローレと何回も繰り返すあの歌。後に知ったのですが邦題は甘い囁き。
話しを元に戻します。
「それはやっぱりパローレじゃない。」と、いうやいなや
まさに as soon asです。
彼女がなんと、コップいっぱいに氷の入ったお水を、僕の顔面に思いっきり浴びせたのです。
いうまでも無く、僕の頭から洋服までビッショリです。
その後すぐ彼女は、走ってお店から出て行ってしまいました。
フローリングの床の上にゴロゴロと氷の大きな音がこだまし、その音の大きさに
周りのお客さんたちの視線も痛いほど僕に注がれてしまいました。勿論前カノも…。
一人残された僕はどうすることもできず目の前にあったおしぼりで濡れた洋服を、拭うしか術がありませんでした。
お店の人が、慌てて氷を拾いながら僕に近づいて来て、気の毒そうに囁いたのです。
「おしぼりお持ちしますか?」
僕にしてみればとてもありがたい甘い囁きでしたが、
「聞く前に早く持ってコーイ」と声にならない声を心の中で思いっきりあげていました。
「大丈夫です。」
そう言って何事もなっかったかのように、僕はお皿に残っていたチーズを食べたのでした。
それからというもの、お客様の声にならない声を聞けるよう日々努めている次第です。